CTEPHの検査
監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授
診察から始まり、詳しい検査に進み診断を確定します。
検査の流れ
CTEPH[chronic thromboembolic pulmonary hypertension:慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症(まんせいけっせんそくせんせいはいこうけつあつしょう)]と診断されるまでには、上図のような流れで、いくつかの検査が⾏われます。
また、CTEPHと診断された後も、治療⽅針の検討や経過の確認のため、同様の検査を繰り返し⾏うことがあります。
STEP1 診察
CTEPHの患者さんは息切れをきっかけに受診することが多く、まずは、息切れを含む現在の症状や今までの経過を医師が問診します。肺や⼼臓の⾳を聞いたり、⼿や脚、顔のむくみなどから、体を動かしたとき(階段を上ったり、重いものを持ったりしたとき)の息切れが、他の病気が原因ではなく、肺⾼⾎圧症によるものかを検討します。
STEP2 肺⾼⾎圧症かどうかを探る検査
診察で肺高血圧症が疑われると、一般的な血液検査や尿検査の他に、おもに以下の表のような検査を行って、肺高血圧症かどうかを確認します。
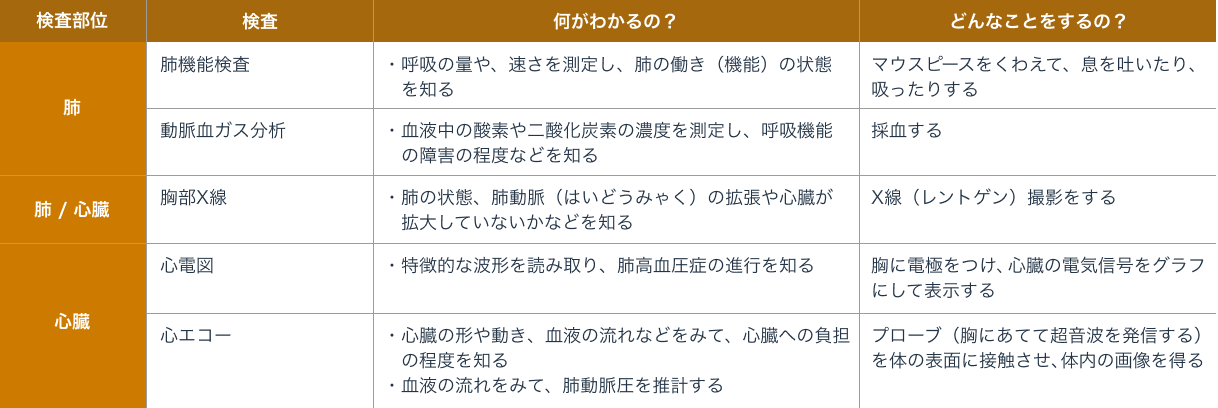
上記、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールをすると続きを見ることができます。
STEP3 確定診断のためのさらに詳しい検査
STEP2の検査で強く肺⾼⾎圧症が疑われる場合、以下の表に⽰す精密検査を⾏い原因を確認します。
なお、⾎液検査は、肺⾼⾎圧症の原因となる疾患の有無だけでなく、右⼼不全(うしんふぜん)の進⾏の程度や、肝機能の異常などがわかるため、適宜⾏われます。
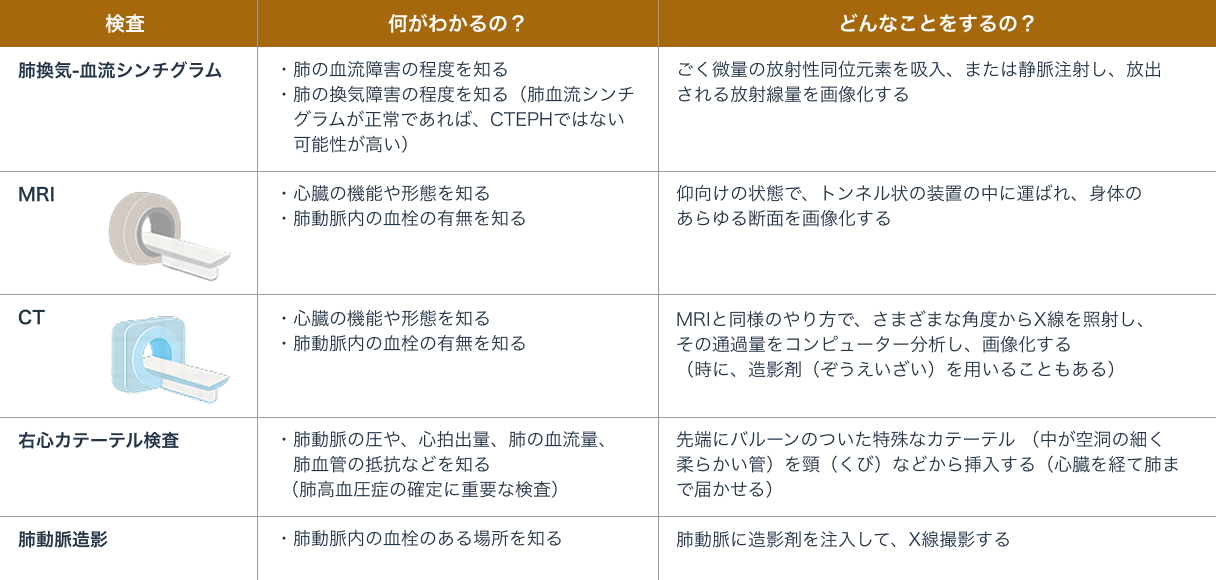
上記、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールをすると続きを見ることができます。
STEP4 CTEPHの確定診断
3ヵ月以上の抗凝固療法を行ったうえで、これらの検査結果から総合的に判断し、CTEPHと確定診断します。また、精密検査の結果は治療方針の判定にも使われます。

監修:福本 義弘 先⽣
久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授
医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。
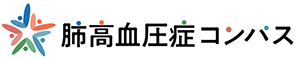
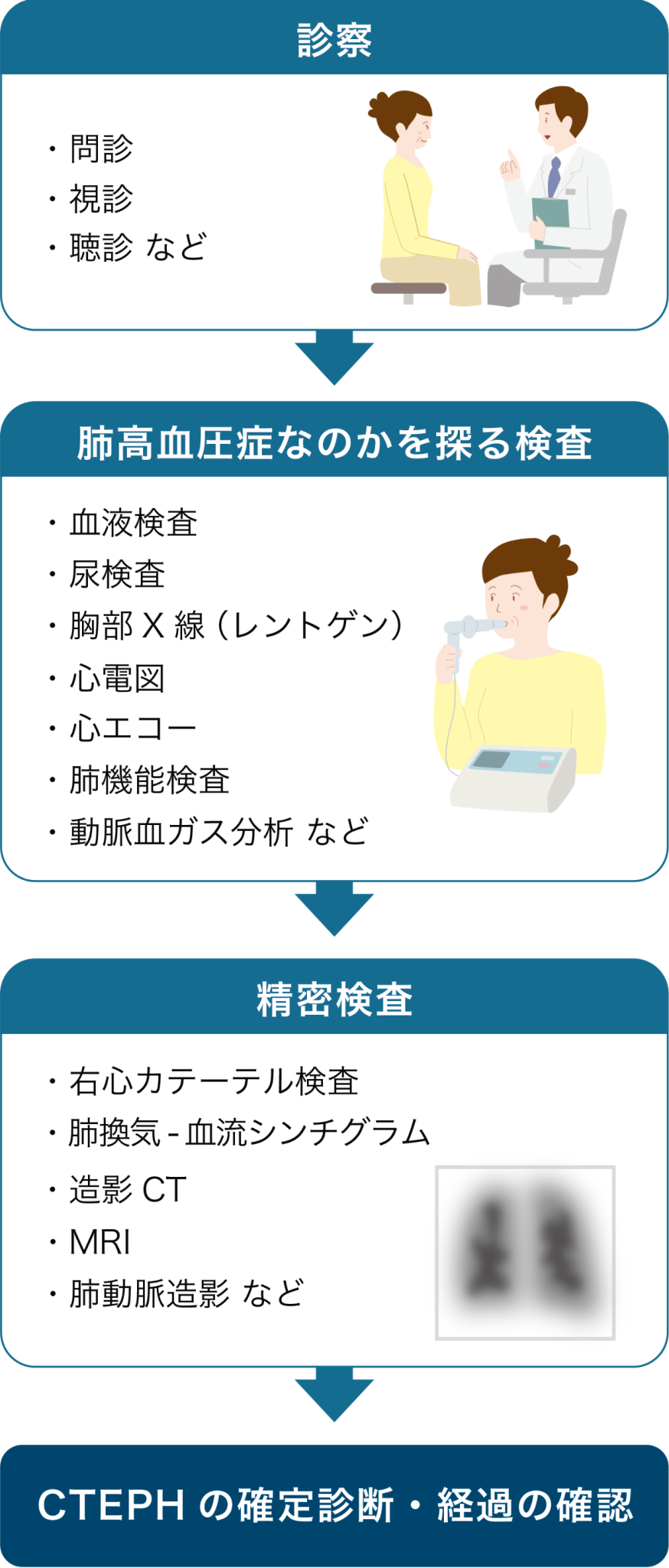


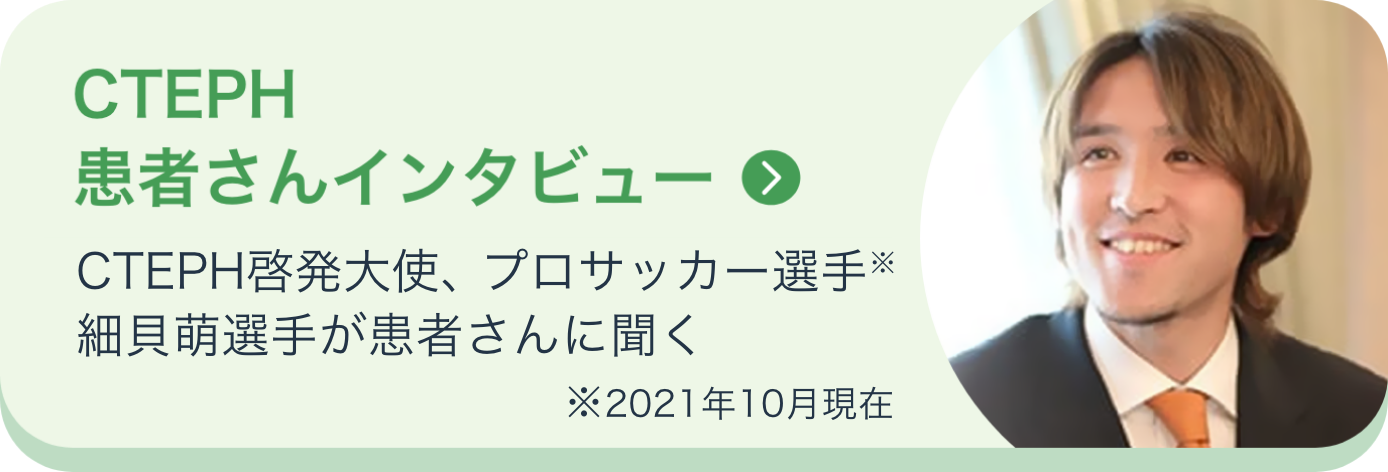
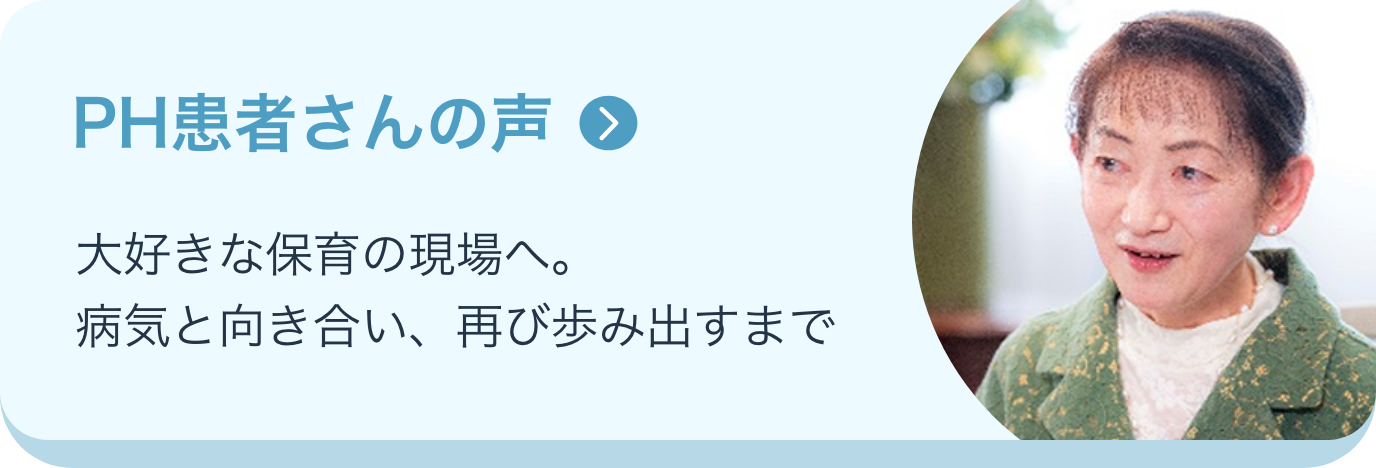
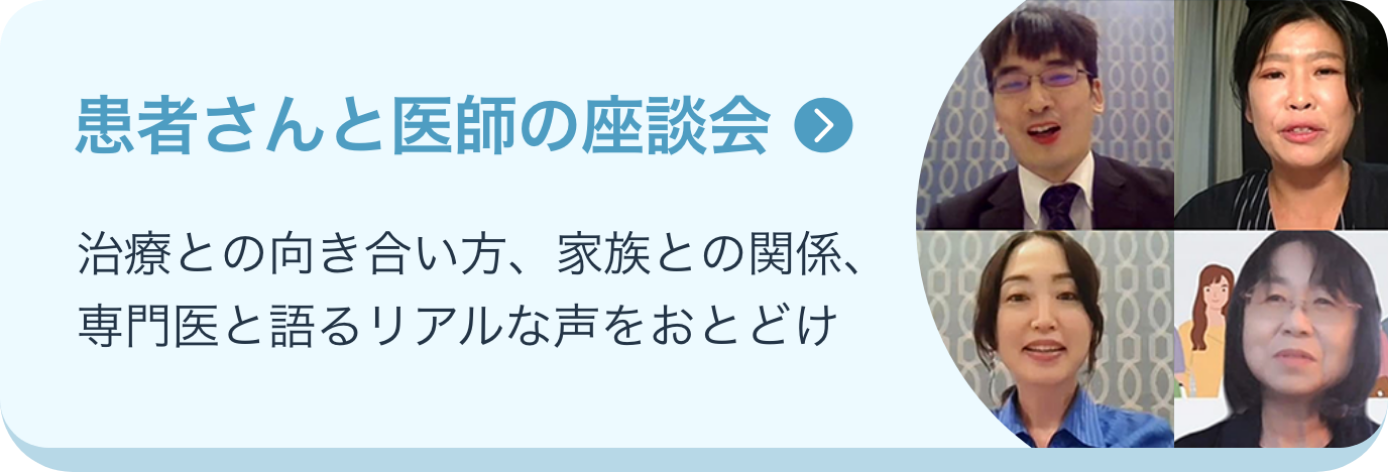

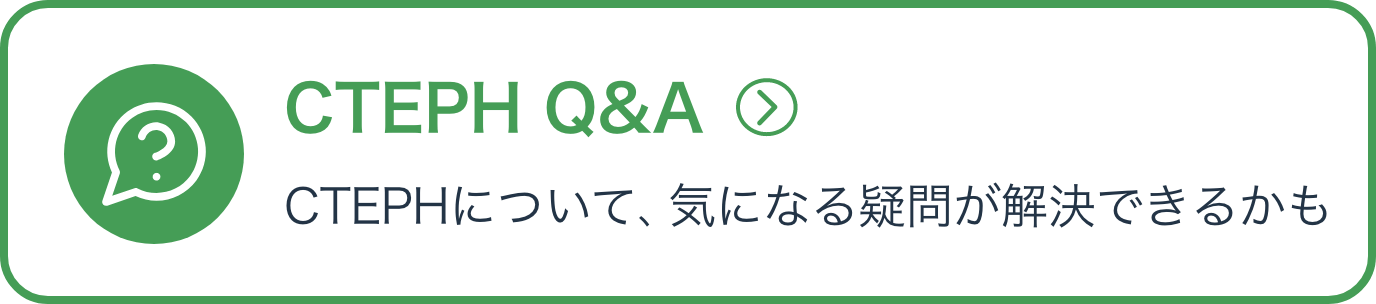

⽬次
① 診察
② 肺⾼⾎圧症かどうかを探る検査
③ 確定診断のためのさらに詳しい検査
④ CTEPHの確定診断