PAHとは?
監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授
PAHとは?
「肺動脈性肺⾼⾎圧症(PAH)」は、肺の細い⾎管が異常に狭くなることで「肺動脈」にかかる圧が⾼くなる病気です。
肺動脈(はいどうみゃく)にかかる圧(肺動脈圧)は、肺の細い⾎管が異常に狭くなり、⾎液が流れにくくなることで⾼まります。肺動脈圧が⾼まると⼼臓に負担がかかり、息切れなどの症状が出てきます。
⾎管が狭くなる原因として、⾎管が収縮すること、⾎管の細胞が異常に増殖し、⾎管の壁が厚くなることがわかっており、⾎管の細胞が異常に増殖し、⾎管の壁が厚くなることが肺動脈性肺⾼⾎圧症(Pulmonary Arterial Hypertension:PAH)の根本原因と考えられています。
PAHが進⾏すると、肺だけでなく⼼臓にも影響を及ぼし、さまざまな症状があらわれます。
PAHでは、右⼼室の負担を減らし、右⼼不全を引き起こさないように、また悪化させないように治療を⾏います。
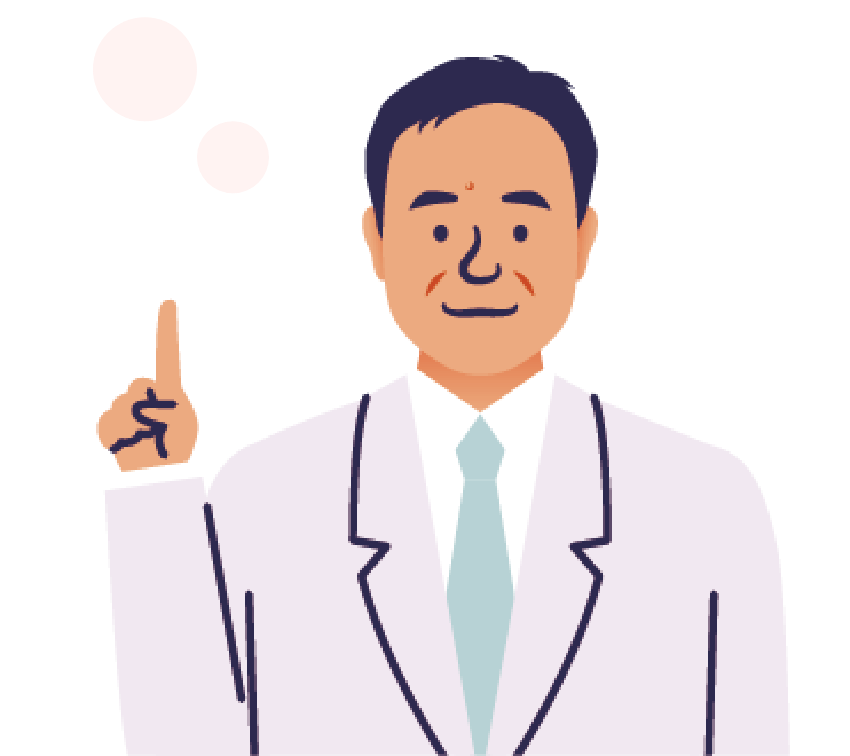
PAHの分類
PAHは肺⾼⾎圧症(PH)の中の1つです。発症の原因によって分類され、原因に応じて治療⽅針が異なります。
肺⾼⾎圧症(Pulmonary Hypertension: PH)は第1群〜第5群に分けられ、肺動脈性肺⾼⾎圧症(Pulmonary Arterial Hypertension:PAH)は第1群に分類されます。
さらに、第1群は発症の原因によって、下記の6つに分類されます。
⽇本循環器学会/⽇本肺⾼⾎圧・肺循環学会.2025年改訂版肺⾎栓塞栓症・深部静脈⾎栓症および肺⾼⾎圧症に関するガイドラインより作成
発症の原因によって治療⽅針が異なります。ご⾃⾝のPAHの原因を知っておくことは治療を受けるうえでとても⼤切です。
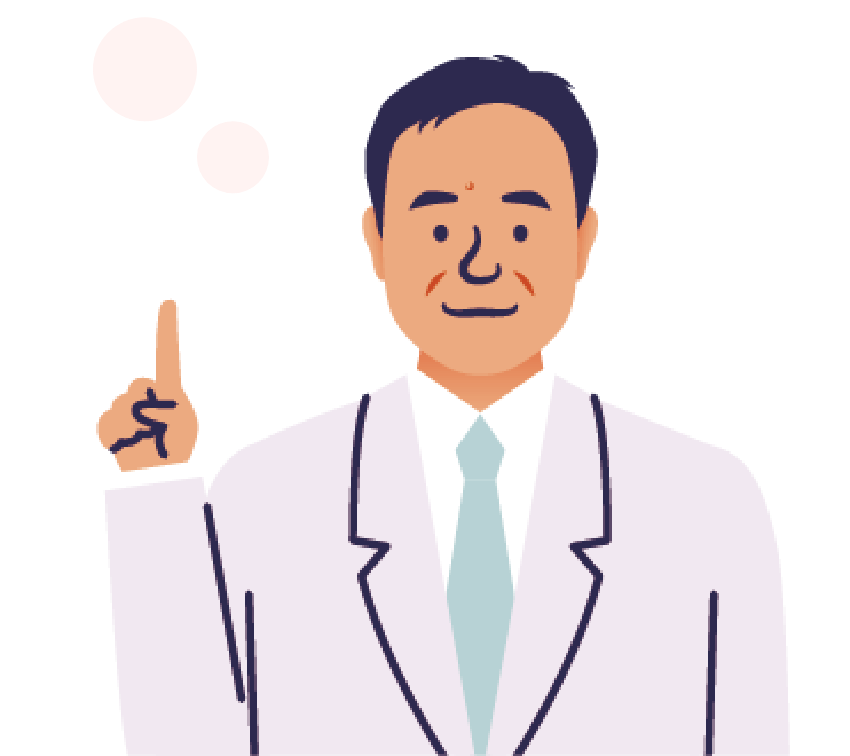

監修:福本 義弘 先⽣
久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授
医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。
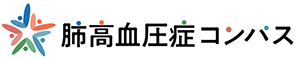




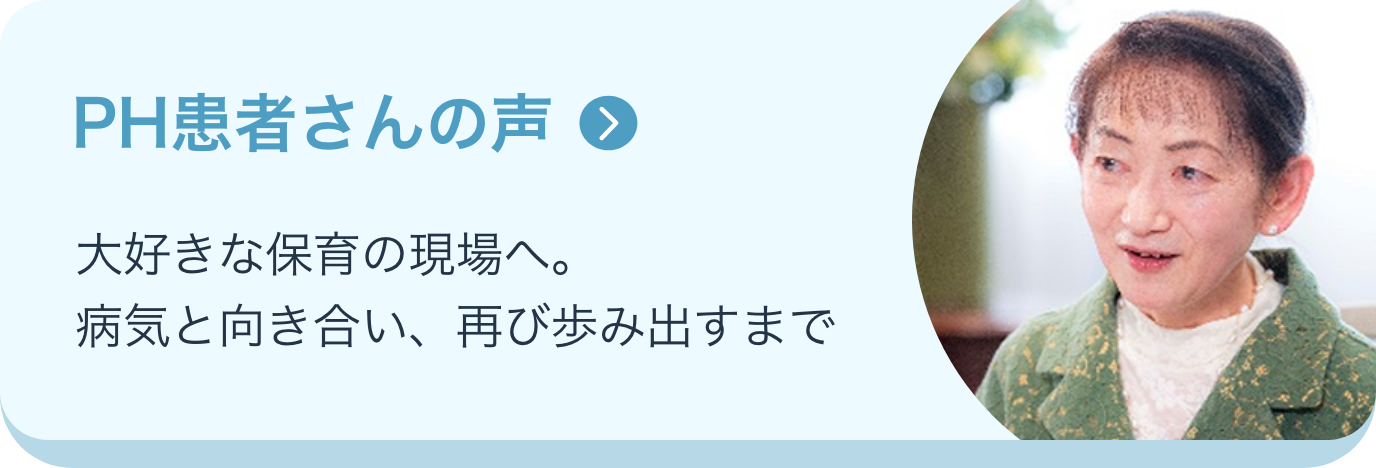
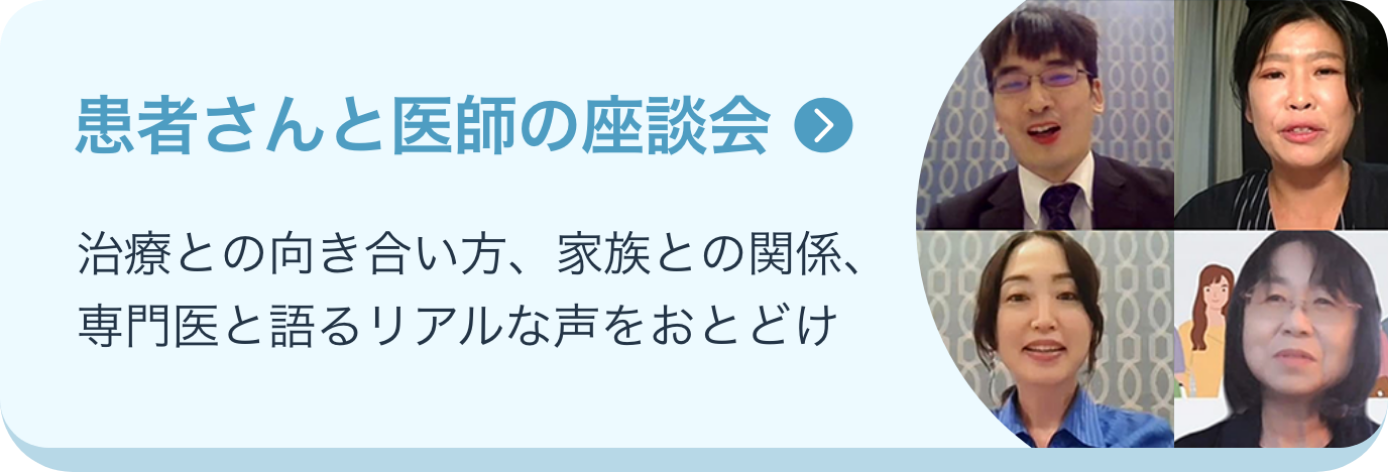
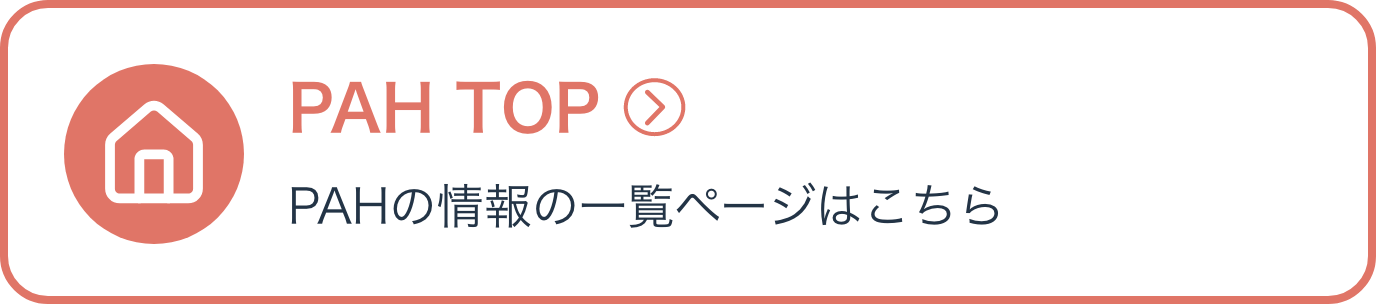
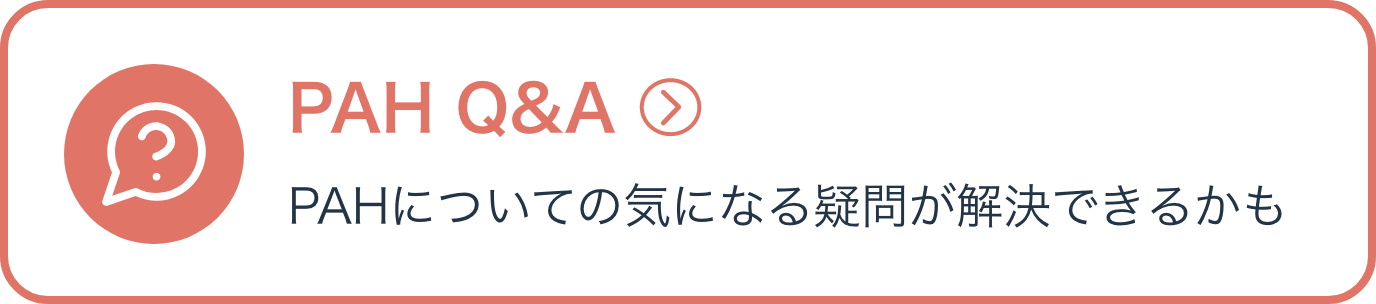

⽬次