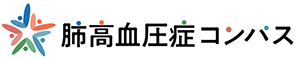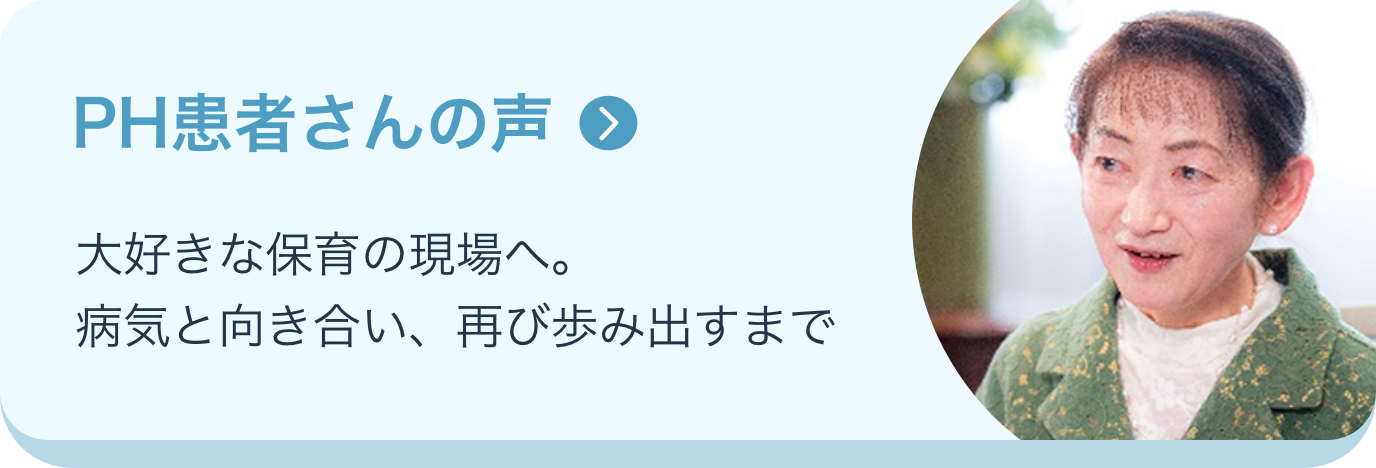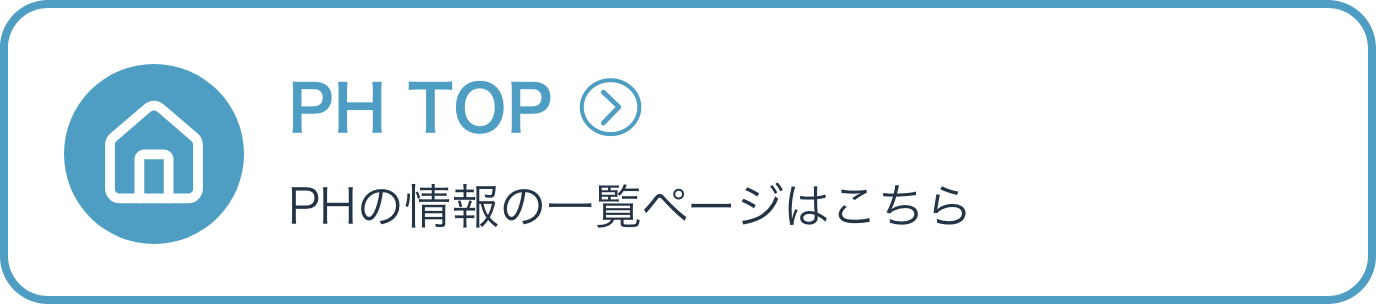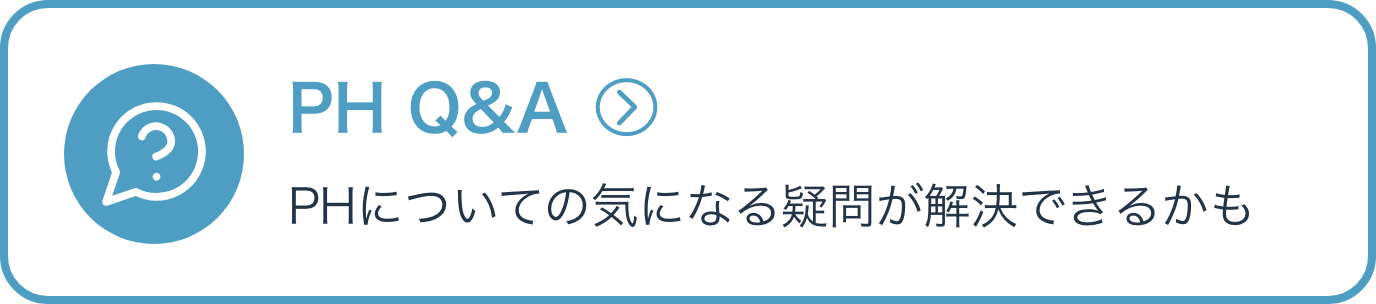後悔しない⼈⽣を過ごすために
〜患者さんが⾃分らしく⽣きるための(意思決定)⽀援〜

肺⾼⾎圧症により、趣味や仕事などを制限されて「⾃分らしく⽣きる」ことが難しい患者さんは多くいらっしゃると思います。今回は、NPO法⼈ PAHの会 理事⻑の村上さんの司会のもと、患者さん代表として吉⽥りょうさん、鶴野千恵さん、医師代表として北海道⼤学の辻野⼀三先⽣にお集まりいただき、現在の患者さんと医師の間にあるギャップや、ギャップに関するアンケート調査、そしてギャップを解消して患者さんが⾃分らしく⽣きていくためのサポートなどについてお話しいただきました。
2022年7⽉15⽇開催
〜 参加者 〜
司会:
村上 紀⼦さん
NPO法⼈ PAHの会 理事⻑。20年近くにわたり患者会に携わる。
パネリスト:
辻野 ⼀三先⽣
北海道⼤学⼤学院医学研究科 呼吸・循環イノベーティブ リサーチ分野 特任教授北海道⼤学医学部を卒業後、同⼤学呼吸器内科(旧:第⼀内科)で⻑年肺⾼⾎圧症の治療に携わる。
吉⽥ りょうさん
PAHの会 会員。
PAHの治療を開始して13年。飲み薬と携帯ポンプによる静脈内投与の薬で治療を継続している。
鶴野 千恵さん
2017年にCTEPHと診断される。北海道⼤学主導の治療にて3回の⼊院で6回のBPA(バルーン肺動脈形成術)を受け、酸素吸⼊療法から解放されて飲み薬による治療を続けている。
患者さんと医師の間にあるギャップ
 本⼼や希望をなかなか⾔い出せない患者さんの存在
本⼼や希望をなかなか⾔い出せない患者さんの存在

村上さん:肺⾼⾎圧症患者さんが、発症してから専⾨医のもとで診察を開始するまでに平均で3年半かかるとのアンケート調査の結果があります(2014年にPAHの会が実施、回答者93名)。3年半もの時間がかかる理由として、専⾨医が少ないことがフォーカスされてきました。しかし、患者会での聴き取り調査では、患者さんがかかりつけ医に、「ほかの医療機関を受診したい」、「セカンドオピニオンを受けたい」と申し出るハードルが⾼く、かかりつけ医に嫌われたくない⼼理が働いているとの意⾒が出ています。やりたいことがあっても先⽣に反対されるから⾔い出しにくいとの声を聞くこともあり、普段の診察で先⽣に遠慮をして悩みや本⼼を伝えられていない実態が考えられます。

辻野先⽣:患者さんの医師に対する遠慮が、専⾨医のもとで診察が始まるまでに時間がかかる要因の⼀つだとの聴き取り調査の結果を聞いて、私は⼤きな衝撃を受けました。というのも、患者さんが症状があっても年齢の影響と考えて病気だと思わない、あるいは医師が別の病気、例えば喘息と判断して様⼦⾒をするといったことが診断の遅れの主な理由と考えていたからです。
村上さん:肺⾼⾎圧症患者さんの⽣命予後は、辻野先⽣をはじめとする専⾨医の先⽣⽅の努⼒により⼤きく改善しました。それによって、患者さんも職場復帰や、就学、結婚など同世代の⼈たちと同じ⽣活をしたいとの希望を持つようになり、⽣命予後を重視する医師側とのギャップが⽣じているのかもしれません。辻野先⽣は、このような患者さんと医師の間のギャップについてどのようにお考えでしょうか。
辻野先⽣:診察では患者さんの病気の悪化を⾒逃さないことが重要であり、患者さんが診察室に⼊っていらしたときに医師が⼀番注意を向けるのは、息切れやむくみなどの患者さんの症状や病状の変化です。患者さんの変化を⾒落とさないことが診察に求められる必要最低限のことですが、患者さんにはそれぞれの⼈⽣があってやりたいこともさまざまだと思います。医師も患者さんの思いに気付いていながら、時間やきっかけがなく、患者さんに聞けずに必要最低限の診察になってしまっているのがほとんどだと思います。しかし、患者さんがどのようなことを希望していらっしゃるかは、薬の使い⽅や副作⽤への対応など治療にも⼤きく影響するため、患者さんの希望や気持ちを伺うことも⼤事だと思っています。
 患者さんの抱える⼼配ごとや不安
患者さんの抱える⼼配ごとや不安
村上さん:吉⽥さんや鶴野さんは、患者さんの⽴場から治療やご⾃⾝の⽣活においてどのような⼼配や不安をお持ちですか。

吉⽥さん:先⽣にもお話ししてあるのですが、最近は使用中の機器の誤作動でアラームが鳴ってカセット交換が必要になるのではないかと外出に不安を感じています。また、今の治療を続けていたら⾃分の体がどのように変化していく可能性があるのか、将来設計や今後の⼼構えのためにも知りたい気持ちがあります。社会復帰ができればいいなと考えていますが、体の負担にならないようにしなければと少し不安もあります。
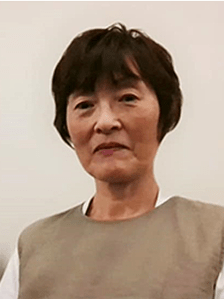
鶴野さん:私が発症した当時は、このまま何もしなければ⼼臓が5年持たないとまで先⽣に⾔われて⾮常に不安でした。実際に当時は10メートル歩いては⽌まりを繰り返し、⽜乳1本持っただけで5メートル歩くのも難しい状況でした。薬を飲み始めてからは、副作⽤で全⾝が痛く、まばたきをしたり、⾷事で⼝を開けたりすることさえ痛い時期があり、別の⾟さがありました。けれどもBPA(バルーン肺動脈形成術)を受けてからお薬の量も減って副作⽤もなくなり、不安や⼼配から解放された気持ちです。
辻野先⽣:BPA治療前の鶴野さんは、普段から調⼦が悪く、薬の副作⽤で体の痛みを訴えられることが何年も続いていました。BPAを受けて酸素吸⼊が不要になり、薬が減ったりやめたりできる患者さんは2-3割程度いらっしゃる印象ですが、鶴野さんはその2-3割に該当する患者さんだと思います。安静時の検査では肺の⾎圧は正常になりましたが、⾎液をさらさらにする薬の服⽤は必要で、今後は運動したときの状態を診る検査を⾏う予定です。
村上さん:体調が良い⼈には良い⼈なりの悩みや不安などがあるのかと思いましたが、まったく⼼配事などありませんか。
鶴野さん:私はあまり我慢をせずに質問したいことがあれば先⽣に随時質問しています。北海道⼤学はチーム制で診療してくださるので、辻野先⽣がお忙しいときはチームのほかの先⽣にお聞きしたり、看護師さんにも質問したりして悩んでいることを解決してきました。ただ、先⽣⽅はお忙しいので、事前に聞きたいことをメモして聞くようにしています。
村上さん:先⽣や看護師さん、チームのほかの先⽣に対して遠慮せずに相談して解決してきたから悩みがないのですね。鶴野さんはタイミングを捉えて先⽣や看護師さんに聞くのが上⼿なのだと思います。けれども⾃分の悩みや不安を抱え込んでしまう患者さんも多く、患者さんと医師の間にギャップが⽣じやすいのかと思います。
 ⼼配や不安を聞いてもらいたいのは?
⼼配や不安を聞いてもらいたいのは?
村上さん:吉⽥さんは、今抱えている⼼配事や不安を誰に聞いてもらいたいと思いますか。
吉⽥さん:普段の診察では、検査結果の説明や、現在の体調、次回診察までの治療内容についての説明で終わってしまうことが多いのですが、⾃分の将来的な⾒通しについては先⽣から改めてお聞きしたいと思います。⼈によっては聞きたくない⽅もいらっしゃるかもしれませんが、先⽣がある程度予測できるのであれば、私は告知してほしいと思います。また、ソーシャルワーカーのような専⾨の⽅が就職活動や就職後も仕事内容について相談できたり間に⼊って調整してくれたりすると⼼強いと思います。
村上さん:⽇本の制度上の問題かもしれませんが、肺⾼⾎圧症患者さんの相談相⼿としてソーシャルワーカーはあまりなじみがありませんね。社会復帰する患者さんが増えていく中で、今後重要になってくるかもしれません。鶴野さんは、悩みがあったら誰に聞いてもらいたいと思いますか。
鶴野さん:私は病気について⾃分で納得したいので、主治医の先⽣やチームの先⽣に聞いてもらいたいと思います。
村上さん:患者会でもやはり先⽣に話を聞いてもらいたいという意⾒が多くあります。⼼配や悩みを先⽣に聞いてほしいと思いながら、先⽣もお忙しくて聞くことが難しいのが実情かもしれません。
患者さんと医療者の間のギャップに関するアンケート調査
村上さん:それではここで、医師が考える患者さんの不安や⼼配と、実際の患者さんの抱える不安や⼼配ごとについてアンケート調査を⾏った結果を辻野先⽣からご紹介いただきます。

辻野先⽣:はい。北海道大学の肺高血圧症患者さんに「今後も肺高血圧症と付き合っていく中で一番心配なことは何ですか?」というアンケート調査を行い、同時に医師・看護師の医療者にその結果を予想してもらいました。普段の診察では、どうしても病状に集中しがちですが、患者さんが本当はどんなことを考えて悩んでいるのか直接聞いてみたいという気持ちからアンケート調査を行いました。そして、医療者が考える患者さんの心配や悩みと実際の患者さんの心配や悩みには、どの程度のギャップがあるのかについても調査しました。対象は、病状の安定した患者さん50名と肺高血圧症診療に携わる医師または看護師の医療者10名です。最初に、肺高血圧症と付き合っていく中で心配なことを、肺高血圧症と関係のないことでもよいので教えてくださいと患者さんにお聞きしました。そして患者さんの回答を分類1の「肺高血圧症に関連する健康上の心配事」、分類2の「肺高血圧症以外の健康上の心配事」、分類3の「家庭、仕事、自然災害など健康に関係しない心配事」、分類4の「心配事なし」の4つに分け、医療者には患者さんの回答の中でどの分類が多いかを予測してもらいました。その結果、医療者の予測としては、分類1の肺高血圧症に関する心配事と予測した人が80%(8名)、分類2のそれ以外の病気に関する心配事と予測した人が20%(2名)でした。しかし、患者さんの実際の回答は、分類1の回答が32%と最も多かったものの、分類4の回答が28%、分類3の回答が26%、分類2の回答が14%と大きく分かれる結果となったのです。医療者の予測が実際の患者さんの回答と分布が異なったのが驚きですが(p=0.0098、Fisher’s test)、特に心配事がないとする分類4の回答が多かったことも印象的でした。
村上さん:患者さんの具体的な回答内容はどのようなものだったのでしょうか。
辻野先⽣:分類1では、病気の悪化が不安、将来酸素が必要になるか不安といった回答があり、分類2では、腎臓病や動脈瘤の⽅が⼼配といった回答がありました。分類3では、アンケート直前にあった地震などの⾃然災害が怖い、年をとることが⼼配、仕事を続けられるか不安といった回答があり、分類4では、先⽣に全部任せているので⼼配していないといった回答がありました。私の感想ですが、通常の診療とは違った質問だったためか、回答する時に患者さんが嬉しそうに話してくださったり、笑顔が⾒られたりしたのが印象的でした。患者さんの思いを共有することが安⼼にもつながり⼤切だと実感しました。また、アンケートを通して、負担のより少ない在宅酸素療法を探したり、合併症の状況を念頭においたり、患者さんの気持ちに寄り添う対応を⼼がけるようになりました。
患者さんと医師の間のギャップの要因
 価値観も置かれた状況も多様な患者さん
価値観も置かれた状況も多様な患者さん
村上さん:辻野先⽣、ありがとうございました。先⽣の⾏ったアンケート調査の結果でも、医師や看護師さんの考える患者さんの⼼配や不安と、患者さんの実際の⼼配や不安の間にはギャップが認められましたが、辻野先⽣はこのギャップの要因としてどのようなものがあるとお考えですか。
辻野先⽣:医師は共通して、患者さんの病気の状態や変化を⾒逃さないことは意識していると思います。しかし、患者さんの考え⽅や価値観はさまざまで、⼼配だから病院に来たい⼈、検査を受けたい⼈もいれば、病院が嫌い、検査もできれば受けたくない⼈もいます。薬に対する考え⽅も、効く可能性があるなら副作⽤に耐えられる⼈もいれば、少しの副作⽤も嫌だという⼈もいます。そうした患者さんのさまざまな考えを知って診療に反映させることはとても⼤切なのは分かっているのですが、現実的には、忙しさに流されて病気や治療の話だけで終わってしまっているのが現状と思います。
村上さん:患者さん側は医師と患者の考えのギャップの要因についてどのように考えていますか。

吉⽥さん:以前通っていた病院は診察する患者数が⼤変多く、先⽣とお話をする時間がなかなか持てませんでしたが、今の病院は以前より患者さんが少なく、先⽣とお話をする時間は改善されたと感じるので、先⽣の忙しさも影響していると思います。けれども今も、病気や⽇々の体調以外について、命に係わるほどのことでもない事などは先⽣に相談しにくいと思う気持ちもあります。でも、普段の⽣活の困りごとなども少しだけ⽿を傾けていただけたら、話を聞いていただけるだけで、ちょっと⼼が軽くなったり、⼼の中が整理できたりするのでは、と思います。病状以外でもテープのかゆみやポンプの重さによる腰痛などに悩んでおり、本当は少しでもご相談して解決したいと思っています。また、体が⾟い時は、検査するだけで疲れてしまい、診察のときには質問にうまく答えられないときもあります。⼤事なことは何回も聞いたり、説明したりしてくださると本当にありがたいと思います。その点では、新型コロナウイルス感染症の影響により、電話による診察が可能になった点は体への負担も軽減されて助かりますね。
村上さん:吉⽥さんはより⾃分らしく⽣活していくために、先⽣からどのようなサポートを受けたいとお考えですか。
吉⽥さん:旅⾏に⾏くとか仕事をするといった⼀歩を踏み出すためにはどうしたらよいのか⼀緒に考えていただいたり、お⼿伝いをしていただけたりしたら嬉しいと思います。
村上さん:病状を考慮して、どんな準備をしたらよいか⼀緒に考えて送り出してもらえたら嬉しいですよね。鶴野さんは病気の診療以外で先⽣に何かサポートを希望されていますか。

鶴野さん:私はかつて⼼臓が5年持たないと⾔われてからちょうど5年経ち、これだけ元気に過ごせていることに満⾜しています。今アルバイトをしているのですが、今年は、治療後の経過観察のため、カテーテル検査をはじめいろいろな検査を⾏い問題なければ、先⽣に相談して、お仕事のことを考えようと思っています。
村上さん:鶴野さんは⼼配を抱えることなく表に出して解決することができ、治療もうまくいった⾮常に幸運な⽅だと思います。
患者さんが⾃分らしく⽣きるための⽀援
 ギャップを解消するための歩み寄り
ギャップを解消するための歩み寄り

村上さん:患者さんの多くは、病気になる前の⽣活に戻りたいと希望されていると思いますが、趣味を制限される、仕事も短時間にせざるを得ないなど⾃分らしさを取り戻すための願いがなかなか受け⼊れられない現状があると思います。また、吉⽥さんのように病気の治療から⼀歩進んだ⾃分の⼈⽣における希望について、なかなか先⽣に打ち明けることが難しい患者さんも多いと思います。こうしたことから⽣まれる患者さんと医師側とのギャップを埋めるために、先⽣の⽴場からどうしたらよいとお考えでしょうか。
辻野先⽣:医師側としては、患者さんの病状を診る必要最低限の診察から⼀歩歩み寄る姿勢が必要だと思います。⼀⾔かけて、⾃分の⽣活のことも考えてくれているのだなと患者さんに感じていただければ、医師と患者さんの関係性も少しずつ変わる可能性があります。また、先ほど、患者さんの希望として旅⾏や仕事などが挙げられましたが、患者さんからそうした具体的な希望を⾔っていただければ、状況や体調にもよりますが、仕事であれば短時間からスタートして、検査をしながら様⼦を⾒て段階的に時間を増やすというように、少しずつやりたいことを広げていくことは可能だと思います。私⾃⾝も、患者さんの望みを取り⼊れて医師と患者さんの共同作業でできることを広げていきたいと希望しています。
村上さん:吉⽥さんは、患者さんの⽴場からギャップを埋めるためにどのようにしたらよいとお考えですか。
吉⽥さん:思い切って主治医の先⽣に相談したり、⾃分でほかにも相談先がないか探したりすることも⼤事だと思いました。また、先⽣とは相性もあると思うので、セカンドオピニオンなどで⾃分に合う先⽣を⾒つけることも⼤切だと思います。私⾃⾝、セカンドオピニオンで出会った先⽣にとても感謝しています。また、先ほど鶴野さんもおっしゃっていましたが、私も診察の待ち時間に聞きたいことをメモして聞くようにしています。診察時間は限られているのでそうした患者側の⼯夫も必要だと思います。
村上さん:聞きたいことや⼼配事などをメモして患者さんも聞く準備をすることも⼤切ですよね。鶴野さんのように聞きたいことを聞く姿勢もギャップを解消するための⼤きな⼀歩だと思います。また、辻野先⽣のように患者さんへのアンケート調査を⾏ってみようとお考えになる先⽣が増えたら、患者さんの悩みも減るのではないかと思います。最後に、辻野先⽣からメッセージをお願いします。
辻野先生:今⽇は患者さんの意識や気持ちを聞かせていただき、貴重なお話が伺えました。私が⾏ったアンケートでも、医療者と患者さんの考えのギャップが明らかになりましたが、患者さんが考えていらっしゃることを患者さん側からも教えていただきたいと思います。⼀⽅で、肺⾼⾎圧症をより多くの医師に認知してもらい、患者さんの速やかな診断と治療につなげていくための努⼒も引き続き⾏っていきたいと思います。
村上さん:多くの患者さんは、肺⾼⾎圧症とともに⾃分らしく、後悔のない⼈⽣を⽣きたいと思っており、病気だからと諦めずに⾃分らしく精いっぱい⽣きたいと願っております。患者さんの悩みや⼼配を先⽣や看護師さんなどに理解していただき、患者さんが有意義な⼈⽣を過ごせるようサポートしていただけたらと願っております。